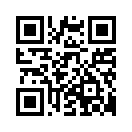2007年06月17日
嵐電 嵐山本線「西院駅」
5月の月刊京つうマガジン「京都 私の好きな駅」の記事UPなんですが、
つまり、先月の宿題を残しておりました本郷剛子です。
6月テーマの「京の名水」が上がっている真最中に、
顰蹙(ひんしゅく)モノですが、駅ネタに暫しお付き合い下さい。
私の好きな駅というか、気になる思い出の駅ということで覗いてみました。
嵐電 嵐山本線「西院駅」です。

2010年3月には、開業100周年を迎えるようですね。

そうそう、つい先日、それまでの愛称だった『嵐電(らんでん)』を、
公式呼称にしたんですよね。

ここ西院駅は、四条通と嵐山線が交差するところにあって、
西大路四条の阪急西院駅にもすぐ近くで、
京都市西部のターミナルエリアでもあります。

しかし、この西院駅の読みですが、
嵐電の西院は「さい」、阪急の西院は「さいいん」。
普通に読んだら、阪急の「さいいん」ですよね。
"さい"とは、どう読んだらそうなるのか不思議です。

その"サイ"の呼称の由来をちょっと調べてみました。
時代はさかのぼって、平安時代の初め、
この付近に淳和天皇の離宮が造営されました。
その離宮は、大内裏から西方にあったことから、
西院(さいいん)と呼ばれるようになりました。
また側を、佐比(さい)大路が走っていたことから、
この辺りの地名を、西院(さい)と呼ぶようになったそうです。
嵐電西院駅のすぐ西、四条通西大路東入北側に、
浄土宗日照山高山寺というお寺があります。
平安期から盛んになっていった地蔵信仰とあいまって、
当寺の子安地蔵が、賽の河原に登場する地蔵であるとされ、
賽(さい)の河原は、ここ西院(さい)の地=西院の河原であると
されるようになっていったようです。


室町時代にあの銀閣寺をつくった足利義政の夫人・日野富子は、
この高山寺・本堂に安置されている子安地蔵に祈願して、
義尚を生んだと伝えられています。

ここ西院駅は、
嵐電の全車両が整備・保守される車庫があるところでもあるのです。
私が電車マニア少年のころ、ここ西院車庫にはよく通ったものです。
昭和50年12月まで、嵐電はホイール式ポール(トロリーポール)という
集電装置を使っていました。
集電装置というと難しいですが、電車の屋根の上に付いている電気を取り
込む装置のことで、現在の一般的な電車では、パンタグラフですよね。
それが、昭和50年まで、嵐電は物干し竿の先端に滑車が付いたような、
一本の棒状のものを使って架線から電気を取っていました。
それを、前年の昭和49年・市電烏丸線の廃線時に廃車となった700形の
Zパンタを受け継ぎ、当時の在籍車両全部をZパンタに換装したのです。
鉄道ファン向けの余談ですが、
国内最後のホイール式ポールの使用されていた営業鉄道は、
ここ嵐電の1975年12月で、
スライダー式ポールの使用の国内最後の営業鉄道は、
なんと叡電の1978年10月でした。
公園なのでの動態保存は、
明治村のN電(京都市電北野線チンチン電車)や梅小路機関車館のN電の
ホイール式ポールの例で見ることができますね。
ところで、梅雨も入ったような入ってないような、
蒸し暑いもう夏のような猛暑ですが、
完全にくたばっている犬を発見してしまいました。

遠くを望むと、陽炎が出ているようです。

そういう時は、西院駅嵐山方面ホームのすぐ横にある
ワンコインドリンクの自販機で好みのジュースを飲みながら、
暫しの涼をとって、休憩するのも乙なもんですよ。

昼を回って午後になると、嵐山方面のホームは日陰になって、
適度に風も吹いてくれて、オープンスペースで気持ちよいのです。
気を遣うほど、わんさか乗降客はないし、無人駅なので出入りは自由だし、
散歩の休憩にはいいのです。

つまり、先月の宿題を残しておりました本郷剛子です。
6月テーマの「京の名水」が上がっている真最中に、
顰蹙(ひんしゅく)モノですが、駅ネタに暫しお付き合い下さい。
私の好きな駅というか、気になる思い出の駅ということで覗いてみました。
嵐電 嵐山本線「西院駅」です。

2010年3月には、開業100周年を迎えるようですね。

そうそう、つい先日、それまでの愛称だった『嵐電(らんでん)』を、
公式呼称にしたんですよね。

ここ西院駅は、四条通と嵐山線が交差するところにあって、
西大路四条の阪急西院駅にもすぐ近くで、
京都市西部のターミナルエリアでもあります。

しかし、この西院駅の読みですが、
嵐電の西院は「さい」、阪急の西院は「さいいん」。
普通に読んだら、阪急の「さいいん」ですよね。
"さい"とは、どう読んだらそうなるのか不思議です。

その"サイ"の呼称の由来をちょっと調べてみました。
時代はさかのぼって、平安時代の初め、
この付近に淳和天皇の離宮が造営されました。
その離宮は、大内裏から西方にあったことから、
西院(さいいん)と呼ばれるようになりました。
また側を、佐比(さい)大路が走っていたことから、
この辺りの地名を、西院(さい)と呼ぶようになったそうです。
嵐電西院駅のすぐ西、四条通西大路東入北側に、
浄土宗日照山高山寺というお寺があります。
平安期から盛んになっていった地蔵信仰とあいまって、
当寺の子安地蔵が、賽の河原に登場する地蔵であるとされ、
賽(さい)の河原は、ここ西院(さい)の地=西院の河原であると
されるようになっていったようです。


室町時代にあの銀閣寺をつくった足利義政の夫人・日野富子は、
この高山寺・本堂に安置されている子安地蔵に祈願して、
義尚を生んだと伝えられています。

ここ西院駅は、
嵐電の全車両が整備・保守される車庫があるところでもあるのです。
私が電車マニア少年のころ、ここ西院車庫にはよく通ったものです。
昭和50年12月まで、嵐電はホイール式ポール(トロリーポール)という
集電装置を使っていました。
集電装置というと難しいですが、電車の屋根の上に付いている電気を取り
込む装置のことで、現在の一般的な電車では、パンタグラフですよね。
それが、昭和50年まで、嵐電は物干し竿の先端に滑車が付いたような、
一本の棒状のものを使って架線から電気を取っていました。
それを、前年の昭和49年・市電烏丸線の廃線時に廃車となった700形の
Zパンタを受け継ぎ、当時の在籍車両全部をZパンタに換装したのです。
鉄道ファン向けの余談ですが、
国内最後のホイール式ポールの使用されていた営業鉄道は、
ここ嵐電の1975年12月で、
スライダー式ポールの使用の国内最後の営業鉄道は、
なんと叡電の1978年10月でした。
公園なのでの動態保存は、
明治村のN電(京都市電北野線チンチン電車)や梅小路機関車館のN電の
ホイール式ポールの例で見ることができますね。
ところで、梅雨も入ったような入ってないような、
蒸し暑いもう夏のような猛暑ですが、
完全にくたばっている犬を発見してしまいました。

遠くを望むと、陽炎が出ているようです。

そういう時は、西院駅嵐山方面ホームのすぐ横にある
ワンコインドリンクの自販機で好みのジュースを飲みながら、
暫しの涼をとって、休憩するのも乙なもんですよ。

昼を回って午後になると、嵐山方面のホームは日陰になって、
適度に風も吹いてくれて、オープンスペースで気持ちよいのです。
気を遣うほど、わんさか乗降客はないし、無人駅なので出入りは自由だし、
散歩の休憩にはいいのです。

Posted by 京つうスタッフ at 01:00│Comments(0)
│’07年5月号☆京都 私の好きな駅