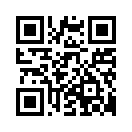2007年06月17日
嵐電 嵐山本線「西院駅」
5月の月刊京つうマガジン「京都 私の好きな駅」の記事UPなんですが、
つまり、先月の宿題を残しておりました本郷剛子です。
6月テーマの「京の名水」が上がっている真最中に、
顰蹙(ひんしゅく)モノですが、駅ネタに暫しお付き合い下さい。
私の好きな駅というか、気になる思い出の駅ということで覗いてみました。
嵐電 嵐山本線「西院駅」です。

2010年3月には、開業100周年を迎えるようですね。

そうそう、つい先日、それまでの愛称だった『嵐電(らんでん)』を、
公式呼称にしたんですよね。

ここ西院駅は、四条通と嵐山線が交差するところにあって、
西大路四条の阪急西院駅にもすぐ近くで、
京都市西部のターミナルエリアでもあります。

しかし、この西院駅の読みですが、
嵐電の西院は「さい」、阪急の西院は「さいいん」。
普通に読んだら、阪急の「さいいん」ですよね。
"さい"とは、どう読んだらそうなるのか不思議です。

その"サイ"の呼称の由来をちょっと調べてみました。
時代はさかのぼって、平安時代の初め、
この付近に淳和天皇の離宮が造営されました。
その離宮は、大内裏から西方にあったことから、
西院(さいいん)と呼ばれるようになりました。
また側を、佐比(さい)大路が走っていたことから、
この辺りの地名を、西院(さい)と呼ぶようになったそうです。
嵐電西院駅のすぐ西、四条通西大路東入北側に、
浄土宗日照山高山寺というお寺があります。
平安期から盛んになっていった地蔵信仰とあいまって、
当寺の子安地蔵が、賽の河原に登場する地蔵であるとされ、
賽(さい)の河原は、ここ西院(さい)の地=西院の河原であると
されるようになっていったようです。


室町時代にあの銀閣寺をつくった足利義政の夫人・日野富子は、
この高山寺・本堂に安置されている子安地蔵に祈願して、
義尚を生んだと伝えられています。

ここ西院駅は、
嵐電の全車両が整備・保守される車庫があるところでもあるのです。
私が電車マニア少年のころ、ここ西院車庫にはよく通ったものです。
昭和50年12月まで、嵐電はホイール式ポール(トロリーポール)という
集電装置を使っていました。
集電装置というと難しいですが、電車の屋根の上に付いている電気を取り
込む装置のことで、現在の一般的な電車では、パンタグラフですよね。
それが、昭和50年まで、嵐電は物干し竿の先端に滑車が付いたような、
一本の棒状のものを使って架線から電気を取っていました。
それを、前年の昭和49年・市電烏丸線の廃線時に廃車となった700形の
Zパンタを受け継ぎ、当時の在籍車両全部をZパンタに換装したのです。
鉄道ファン向けの余談ですが、
国内最後のホイール式ポールの使用されていた営業鉄道は、
ここ嵐電の1975年12月で、
スライダー式ポールの使用の国内最後の営業鉄道は、
なんと叡電の1978年10月でした。
公園なのでの動態保存は、
明治村のN電(京都市電北野線チンチン電車)や梅小路機関車館のN電の
ホイール式ポールの例で見ることができますね。
ところで、梅雨も入ったような入ってないような、
蒸し暑いもう夏のような猛暑ですが、
完全にくたばっている犬を発見してしまいました。

遠くを望むと、陽炎が出ているようです。

そういう時は、西院駅嵐山方面ホームのすぐ横にある
ワンコインドリンクの自販機で好みのジュースを飲みながら、
暫しの涼をとって、休憩するのも乙なもんですよ。

昼を回って午後になると、嵐山方面のホームは日陰になって、
適度に風も吹いてくれて、オープンスペースで気持ちよいのです。
気を遣うほど、わんさか乗降客はないし、無人駅なので出入りは自由だし、
散歩の休憩にはいいのです。

つまり、先月の宿題を残しておりました本郷剛子です。
6月テーマの「京の名水」が上がっている真最中に、
顰蹙(ひんしゅく)モノですが、駅ネタに暫しお付き合い下さい。
私の好きな駅というか、気になる思い出の駅ということで覗いてみました。
嵐電 嵐山本線「西院駅」です。

2010年3月には、開業100周年を迎えるようですね。

そうそう、つい先日、それまでの愛称だった『嵐電(らんでん)』を、
公式呼称にしたんですよね。

ここ西院駅は、四条通と嵐山線が交差するところにあって、
西大路四条の阪急西院駅にもすぐ近くで、
京都市西部のターミナルエリアでもあります。

しかし、この西院駅の読みですが、
嵐電の西院は「さい」、阪急の西院は「さいいん」。
普通に読んだら、阪急の「さいいん」ですよね。
"さい"とは、どう読んだらそうなるのか不思議です。

その"サイ"の呼称の由来をちょっと調べてみました。
時代はさかのぼって、平安時代の初め、
この付近に淳和天皇の離宮が造営されました。
その離宮は、大内裏から西方にあったことから、
西院(さいいん)と呼ばれるようになりました。
また側を、佐比(さい)大路が走っていたことから、
この辺りの地名を、西院(さい)と呼ぶようになったそうです。
嵐電西院駅のすぐ西、四条通西大路東入北側に、
浄土宗日照山高山寺というお寺があります。
平安期から盛んになっていった地蔵信仰とあいまって、
当寺の子安地蔵が、賽の河原に登場する地蔵であるとされ、
賽(さい)の河原は、ここ西院(さい)の地=西院の河原であると
されるようになっていったようです。


室町時代にあの銀閣寺をつくった足利義政の夫人・日野富子は、
この高山寺・本堂に安置されている子安地蔵に祈願して、
義尚を生んだと伝えられています。

ここ西院駅は、
嵐電の全車両が整備・保守される車庫があるところでもあるのです。
私が電車マニア少年のころ、ここ西院車庫にはよく通ったものです。
昭和50年12月まで、嵐電はホイール式ポール(トロリーポール)という
集電装置を使っていました。
集電装置というと難しいですが、電車の屋根の上に付いている電気を取り
込む装置のことで、現在の一般的な電車では、パンタグラフですよね。
それが、昭和50年まで、嵐電は物干し竿の先端に滑車が付いたような、
一本の棒状のものを使って架線から電気を取っていました。
それを、前年の昭和49年・市電烏丸線の廃線時に廃車となった700形の
Zパンタを受け継ぎ、当時の在籍車両全部をZパンタに換装したのです。
鉄道ファン向けの余談ですが、
国内最後のホイール式ポールの使用されていた営業鉄道は、
ここ嵐電の1975年12月で、
スライダー式ポールの使用の国内最後の営業鉄道は、
なんと叡電の1978年10月でした。
公園なのでの動態保存は、
明治村のN電(京都市電北野線チンチン電車)や梅小路機関車館のN電の
ホイール式ポールの例で見ることができますね。
ところで、梅雨も入ったような入ってないような、
蒸し暑いもう夏のような猛暑ですが、
完全にくたばっている犬を発見してしまいました。

遠くを望むと、陽炎が出ているようです。

そういう時は、西院駅嵐山方面ホームのすぐ横にある
ワンコインドリンクの自販機で好みのジュースを飲みながら、
暫しの涼をとって、休憩するのも乙なもんですよ。

昼を回って午後になると、嵐山方面のホームは日陰になって、
適度に風も吹いてくれて、オープンスペースで気持ちよいのです。
気を遣うほど、わんさか乗降客はないし、無人駅なので出入りは自由だし、
散歩の休憩にはいいのです。

2007年06月04日
阪急河原町駅
こんにちは、ロディです。やっと駅ブログに参戦です。
今月のテーマは私の好きな駅と言うことで
阪急河原町駅を紹介したいと思います。

専門学校に通っていた頃からのお付き合いです。
思い出がつまり過ぎていてほんと大好きなんです
毎朝駅まで猛ダッシュしてました。時刻表が頭に入っていない私は
これを見て遅刻かセーフかを判断してました。 このダメッぷりは相変わらず…
このダメッぷりは相変わらず…

駅が好きというより河原町駅から乗り込む電車がすきです

梅田に行くときは小旅行気分で楽しんでいます 季節ごとに変わる沿線の風景がまた最高です
季節ごとに変わる沿線の風景がまた最高です
すごくはっきりと四季の移り変わりが分かるんです。
ちなみに帰りの電車はたいがい爆睡しているので電車に乗ってる時間を長く感じたことがありません
夜の11時くらいの駅はさみしいのでちょっと苦手…。
課題で残ったときにたどりつくのがこの時間帯だったので
なんかさみしい気持ちにさせられるんでしょうか

いかがだったでしょう?日ごろ利用している駅にちょっと
注意を向けてみたら駅そのものより思い出にふけってしまうこと間違いなしです
今月のテーマは私の好きな駅と言うことで
阪急河原町駅を紹介したいと思います。

専門学校に通っていた頃からのお付き合いです。
思い出がつまり過ぎていてほんと大好きなんです

毎朝駅まで猛ダッシュしてました。時刻表が頭に入っていない私は
これを見て遅刻かセーフかを判断してました。
 このダメッぷりは相変わらず…
このダメッぷりは相変わらず…
駅が好きというより河原町駅から乗り込む電車がすきです


梅田に行くときは小旅行気分で楽しんでいます
 季節ごとに変わる沿線の風景がまた最高です
季節ごとに変わる沿線の風景がまた最高です
すごくはっきりと四季の移り変わりが分かるんです。
ちなみに帰りの電車はたいがい爆睡しているので電車に乗ってる時間を長く感じたことがありません

夜の11時くらいの駅はさみしいのでちょっと苦手…。
課題で残ったときにたどりつくのがこの時間帯だったので
なんかさみしい気持ちにさせられるんでしょうか


いかがだったでしょう?日ごろ利用している駅にちょっと
注意を向けてみたら駅そのものより思い出にふけってしまうこと間違いなしです

2007年06月03日
京都市営地下鉄東西線 「石田駅」
こんばんは。
京つうスタッフのムーミンパパです。
今回、5月の京つうマガジンのテーマは「好きな駅」です。
私が紹介させていただく駅は通勤時に乗降している京都市営地下鉄東西線「石田駅」です。
東西線(とうざいせん)は、京都府宇治市の六地蔵駅から京都市中京区の二条駅までを結ぶ京都市営地下鉄の路線である。御池線(おいけせん)と呼ばれることもあります。




京都市で2番目の市営地下鉄路線として開業した。京都市中心部と同市東南部の山科区・伏見区との通勤輸送、及び滋賀県大津との都市間輸送の一部を担う路線であり、1日平均12万人が利用しています。



京都市営地下鉄で唯一発車メロディがあるが、4曲全てが京都の長い歴史を反映してか古風な雰囲気の曲である。製作した櫻井音楽工房/テイチクエンタテインメントはこの実績を買われ、後にJR東日本の発車メロディを担当することになる。曲名は以下の通り。
1、古都の朝靄(各駅共通・六地蔵行き)
2、醍醐寺の鶯(各駅共通・二条行き)
3、春開き(御陵駅のみ・京都市役所前行き)
4、詩仙堂猪脅し(御陵駅のみ・浜大津行き)


都市中心部で東西方向に走っていることから、東西線と名付けられているが、東西方向に走っているのは全体の半分程度です。
また、各駅毎にステーションカラーと呼ばれるシンボルカラーが選定されており、ホームドアのほか、駅名表示部、駅名パネル、駅務室の外壁、エレベーターの扉などがその色で統一されている。

駅から東へ徒歩で20分ほど行くと、1月の「裸踊り」で知られる日野の法界寺がある。
その他、醍醐寺、日野誕生院なども近くにあります。
京つうスタッフのムーミンパパです。
今回、5月の京つうマガジンのテーマは「好きな駅」です。
私が紹介させていただく駅は通勤時に乗降している京都市営地下鉄東西線「石田駅」です。
東西線(とうざいせん)は、京都府宇治市の六地蔵駅から京都市中京区の二条駅までを結ぶ京都市営地下鉄の路線である。御池線(おいけせん)と呼ばれることもあります。
京都市で2番目の市営地下鉄路線として開業した。京都市中心部と同市東南部の山科区・伏見区との通勤輸送、及び滋賀県大津との都市間輸送の一部を担う路線であり、1日平均12万人が利用しています。
京都市営地下鉄で唯一発車メロディがあるが、4曲全てが京都の長い歴史を反映してか古風な雰囲気の曲である。製作した櫻井音楽工房/テイチクエンタテインメントはこの実績を買われ、後にJR東日本の発車メロディを担当することになる。曲名は以下の通り。
1、古都の朝靄(各駅共通・六地蔵行き)
2、醍醐寺の鶯(各駅共通・二条行き)
3、春開き(御陵駅のみ・京都市役所前行き)
4、詩仙堂猪脅し(御陵駅のみ・浜大津行き)
都市中心部で東西方向に走っていることから、東西線と名付けられているが、東西方向に走っているのは全体の半分程度です。
また、各駅毎にステーションカラーと呼ばれるシンボルカラーが選定されており、ホームドアのほか、駅名表示部、駅名パネル、駅務室の外壁、エレベーターの扉などがその色で統一されている。
駅から東へ徒歩で20分ほど行くと、1月の「裸踊り」で知られる日野の法界寺がある。
その他、醍醐寺、日野誕生院なども近くにあります。
2007年05月31日
叡電出町柳駅
こんばんは。
京つうスタッフのもーちゃんです。
今日、鴨川にかかる松原橋を渡っていると、そこから四条にかけて鮎釣りをする太公望が何人も立っているのを見かけました。
これから夏にかけて、鮎のおいしい季節です。
今年も口にする機会があればといいなぁと思います。
さて、5月の京つうマガジンのテーマは「好きな駅」です。
僕が好きな駅は「叡電出町柳駅」です。

賀茂川と高野川が交わる出町にある「叡電」の始発駅。
「叡電」はそこから北の方へ向かいます。
最初は高野川と平行するように北に伸びる「叡電」ですが、「宝ヶ池」で「八瀬比叡山口」行きとわかれた鞍馬線は岩倉の方をぐるっとまわって、今度は賀茂川の上流、鞍馬川に沿って線路が延び、「貴船口」から終点「鞍馬」へと静かな山あいを縫うように走ります。
実は大学生の頃、「二軒茶屋駅」の近くに住んでいました。
なんにも予定のない日にはよく「出町柳」まで出て、出町の三角州あたりの河原でのんびりと過ごしました。
川べりに寝転がって本を読んだり、ビールを飲んだりしている間にゆっくりと時間が過ぎていきました。
いまよりずっと贅沢な時間が僕をやさしく包みこんでいました。
その頃、京阪はまだ三条止まりでした。
京阪が出町柳まで延伸したのは1989年10月5日でした。それ以前と、それ以降では「出町柳駅」のもつ意味はすっかり変わってしまいました。(そういえば、当時は京福だったのです!)
「元田中駅」や「茶山駅」はまだその当時の匂いが残っているような気がします。
そんなとりとめのないことを思いだしながら、僕は少しセンチメンタルな気分になってしまいました。
大学生の僕は、たぶん卒業したら田舎に帰るものだと、自分の未来についてぼんやりと考えていました。
それから20年がたちました。不思議なことに今も毎日、出町の三角州を見ながら、事務所に通っています・・・。
■叡山電鉄株式会社HP
京つうスタッフのもーちゃんです。
今日、鴨川にかかる松原橋を渡っていると、そこから四条にかけて鮎釣りをする太公望が何人も立っているのを見かけました。
これから夏にかけて、鮎のおいしい季節です。
今年も口にする機会があればといいなぁと思います。
さて、5月の京つうマガジンのテーマは「好きな駅」です。
僕が好きな駅は「叡電出町柳駅」です。
賀茂川と高野川が交わる出町にある「叡電」の始発駅。
「叡電」はそこから北の方へ向かいます。
最初は高野川と平行するように北に伸びる「叡電」ですが、「宝ヶ池」で「八瀬比叡山口」行きとわかれた鞍馬線は岩倉の方をぐるっとまわって、今度は賀茂川の上流、鞍馬川に沿って線路が延び、「貴船口」から終点「鞍馬」へと静かな山あいを縫うように走ります。
実は大学生の頃、「二軒茶屋駅」の近くに住んでいました。
なんにも予定のない日にはよく「出町柳」まで出て、出町の三角州あたりの河原でのんびりと過ごしました。
川べりに寝転がって本を読んだり、ビールを飲んだりしている間にゆっくりと時間が過ぎていきました。
いまよりずっと贅沢な時間が僕をやさしく包みこんでいました。
その頃、京阪はまだ三条止まりでした。
京阪が出町柳まで延伸したのは1989年10月5日でした。それ以前と、それ以降では「出町柳駅」のもつ意味はすっかり変わってしまいました。(そういえば、当時は京福だったのです!)
「元田中駅」や「茶山駅」はまだその当時の匂いが残っているような気がします。
そんなとりとめのないことを思いだしながら、僕は少しセンチメンタルな気分になってしまいました。
大学生の僕は、たぶん卒業したら田舎に帰るものだと、自分の未来についてぼんやりと考えていました。
それから20年がたちました。不思議なことに今も毎日、出町の三角州を見ながら、事務所に通っています・・・。
■叡山電鉄株式会社HP
2007年05月28日
京阪七条駅
どうもこんばんわ。 京つうスタッフの「おけいはんファン」こと、スネ夫です。
今月のテーマは、「京都 私の好きな駅」という事なんですが…。
ぼくの好きな駅は、やはり良く利用する「京阪七条駅」でございます。

ここら辺に引っ越してきて、もう5年位。
それまではあまり「電車」を利用する事は無かったのですが、こっち来てから乗りまくりです。




















こんな風に。 ↓

まずは階段を下りて、改札へ向かいます。

そして地下の連絡通路を通り、反対側へ行くのです。(三条方面へ向かうから)

そしたら、何故か

なぁんんだあ、これ?
不思議なオブジェがございます。
 骨?
骨?

切符買って、改札を通ったら

こんな感じです。




















七条駅は、「K特急・特急・準急・普通」 全て停まります。
これは非常にありがたい。 超便利。 1本位は見送っても平気です。
…が、しかし。
今では思い出話ですが、
三条(木屋町)で飲んでいて帰りの電車で眠ってしまい、寝過ごした経験が何度かあります。
「七条」で降りたいのに「丹波橋」まで行ってしまい、慌てて戻ったにも関わらず
また寝ちゃって「出町柳」へ。
ガッカリしながら改めて乗り換えのに、またまた寝ちゃって「枚方市」まで…
なかなか家に帰れないのです…。
これは非常に悲しくなりました。
全部停車しても、こうなったら関係ないです。
みなさんも飲み過ぎには注意しましょう。

今月のテーマは、「京都 私の好きな駅」という事なんですが…。
ぼくの好きな駅は、やはり良く利用する「京阪七条駅」でございます。
ここら辺に引っ越してきて、もう5年位。
それまではあまり「電車」を利用する事は無かったのですが、こっち来てから乗りまくりです。




















こんな風に。 ↓
まずは階段を下りて、改札へ向かいます。
そして地下の連絡通路を通り、反対側へ行くのです。(三条方面へ向かうから)
そしたら、何故か
なぁんんだあ、これ?
不思議なオブジェがございます。

 骨?
骨?切符買って、改札を通ったら
こんな感じです。




















七条駅は、「K特急・特急・準急・普通」 全て停まります。
これは非常にありがたい。 超便利。 1本位は見送っても平気です。
…が、しかし。
今では思い出話ですが、
三条(木屋町)で飲んでいて帰りの電車で眠ってしまい、寝過ごした経験が何度かあります。
「七条」で降りたいのに「丹波橋」まで行ってしまい、慌てて戻ったにも関わらず
また寝ちゃって「出町柳」へ。

ガッカリしながら改めて乗り換えのに、またまた寝ちゃって「枚方市」まで…

なかなか家に帰れないのです…。
これは非常に悲しくなりました。
全部停車しても、こうなったら関係ないです。
みなさんも飲み過ぎには注意しましょう。